ダートフィッシュは数多くの大学に導入いただいております。その中でも10年以上「弓道」の授業や部活でソフトウェアを使いこなしている國學院大學の山田先生に取材をしてきました。スポーツの指導者は必見です。

こんにちは。ダートフィッシュ・ジャパンのSEOです。
今回は弓道場にフィードバック環境が整っている國學院大學たまプラーザキャンパスに来ました。

山田先生、本日はよろしくお願いします。

今回のインタビュイーの山田先生。國學院大學の人間開発学部 健康体育学科所属。弓道の授業や部活をはじめ様々な場面でダートフィッシュを長年活用している。

よろしくお願いします。

ダートフィッシュについては、どこで知ったのでしょうか?

12年ほど前に、同じ学科の教員から「ダートフィッシュという面白そうなソフトがあるよ」と偶然話を聞きました。
その後、とある大学で体操の分析と教材作りの用途で使っていることを知ったり、テレビで色々な種目の技術を解明する番組でストロモーション機能を見つけて、体育の教材作りや研究に使いたい!と思ったのがきっかけです。

弓道はその場で動かない状態から28m離れた的に中てる種目のため、フォームの「再現性」がものすごく重要になってきます。
このサイマルカムを使って上手い人に2回、的に射てもらった動作を合成すると、このようにぴったり合います。フォーム再現性の重要性を解説する際に、色々説明をするよりこの動画を1度見せるだけで理解できます。弓道の運動特性とダートフィッシュとの相性がぴったり合うと思いました。

とある学生の1回目と2回目のフォームを「サイマルカム」で合成表示させた様子。動作がきれいに一致していることが分かる。動作の再現性が求められる種目には、ダートフィッシュの「サイマルカム」をはじめ多くの機能で分析とフィードバックができる。

現在はどのように活用していますか?

弓道の授業や部活をメインに使っています。こちらの写真をご覧ください。

射場に設置されたカメラと遅延再生表示をしている大きなモニター。「インジアクション機能」のライブディレイでタイムシフトさせて常に60秒前の様子が表示させている。

弓道場に大きなモニターがありますね!何を表示させているのですか?

姿見と呼ばれる「鏡」から最も近い射位から弓を引く学生のフォームをデジタルカメラやWebカメラで撮影し、ソフトウェアで60秒ほどタイムシフト再生をして表示させています。
引き終わって次の学生に場所を譲りモニターを見に行った頃には、ちょうど60秒前に自分が弓を引いている映像を客観的に見て、自分フォームの変化や手ごたえを確認できるようになっています。この間にカメラやPCは一切操作しません。
タイムシフト再生:指定した秒数分、映像を遅延させて再生する機能。
射場:弓道場の弓を引くエリア

授業内の自主フィードバック環境での活用の流れ。姿見(鏡)の前に設置されたカメラの映像は、 ダートフィッシュ・ソフトウェアで60秒ほどタイムシフト(遅延再生)をさせて大きなモニターに表示している。 常にタイムシフトさせることで、弓を引き終わってモニターの前に移動した頃に、ちょうど自分が弓を引き始めるところからフォームを確認することができる仕組みになっている。 一度設置すればカメラやソフトの操作は全く不要。

何故大きなモニターを取り付けたのですか?

授業に参加する40名ほどの学生が、毎回限られた時間で効率よく学べる環境があると良いなと思っていました。
弓道は「見取り稽古」で上手い人のフォームを観察し、技術の向上を図ることを大事にしているため、一昔前まではカメラ機材など持ち込めるような種目ではありませんでした。
ですが、ここ数年で視聴覚による情報の提供と確認が重要視されるようになり、この弓道場にモニターを付けてもらいました。
見取り稽古:自身の目で見ながら学ぶこと

先生はクラウドで映像共有もされているとお聞きしました。どのように運用しているのか教えてください。

先ほどの授業とは別に、3人1組のグループ毎に「入場」から「行射」、「退場」するまでの一連動作を調和させる「武道と所作礼法」で積極的に使っています。
改善すべき動作や、重要なシーンがあればこのように曲線やコメントを追記して教材を作成し、学生にURLで動画を配信しています。

重要なシーンをスティルショット(静止画)として登録し、コメントやドローイングツールで線や図形を描いてフィードバックを行う。クラウドが導入されたことで、現場で終わっていたフィードバックが今度は復習と予習の資料も提供できるようになって、学生たちの理解するスピードが早くなったとのこと。

授業に導入したメリットはありますか?

導入前は全部わたしが口頭で「3番の人遅い」「1番の人出す足が逆」といったように指導をしていましたが、学生は個々が指導されたことを直そうとするばかりで、グループ全体の3人の動きとしての振り返りができていない印象でした。
導入してからは、自チームの動きを確認して学生自身でも課題をみつけることができました。一方的な指導ではなく、自分たちでディスカッションをして改善する取り組みが増えたため、理解するスピードが上がっています。

自分が教材の対象になると、授業に取り組む姿勢や意識が高くなることが期待できますね!
弓道部ではどのように活用していますか?

タブレット端末で撮影を行い、部員には過去に分析した映像から分かる違いや改善すべき課題を考えてもらっています。

作成された部員ごとにコレクション(フォルダ)には、今まで撮影した分析映像が保管されており、部員はいつでもどこでもパソコンやスマートフォンで閲覧できるようになっている。

フリーハンドで線を描き、具体的にこうすればよいフォームを直感的に理解できるようになっている。数値で示すより、こちらの方がより早く改善されるとのこと。

ドローイングツールのフリーハンドを使っているのですね。
図形や距離の表示もできますが、豊富なツールの中でなぜフリーハンドを使っているのですか?

はじめは言葉だけのアドバイスだったのですが、ある時部員から「腕」をどの程度下げればいいのか教えてほしいと言われたことがありました。
「あと10センチ」や「30度」といったように数値や角度表示によるアドバイスは指導前後の映像を比較する時には有効ですが、直前の試技の指導には、このようにフリーハンドで線を描いたほうが、直感的にすぐ理解できると学生から大変好評です。

今後どんな方にダートフィッシュを使っていただきたいですか?

指導者です。現場で指導している人が、教える場面で自分の思い込みだとか、直感だけで指導するのではなくて、大事なポイントを指導者側が映像を利用して客観的なアドバイスを提供して、学習者が理解し易い環境を作ることが大事だと思います。
信用してもらい、アドバイスを受け入れて、結果を出す。ダートフィッシュで分析した映像があるとお互いが客観的に確認することで、質の高いフィードバックを行うことができます。
今はこういうツールを導入するべき時代だと思います。かゆいところに手が届く機能が多くあるダートフィッシュを是非活用してほしいです。

最後に今後の展望を教えてください!

今まさに、弓道に取り組む人はテクニックに飢えています。自分のフォームがどうなのか昔も今も誰にとっても課題なのです。そういったときに映像は大切な情報源です。
昔から興味のある方は多くいたにも関わらず、なかなか手が出ず敷居が高かったですが、他の種目でそういったツールを多く取り入れるようになった流れがあったこともあり、ようやくハードルが下がってきました。
指導の現場で教える人も、教わる側にしても楽しい環境が広がっていくと思います。

今後の参考にさせていただきます。
本日はどうもありがとうございました。今後もダートフィッシュ・ジャパンをよろしくお願いします。

【インタビュイー】
山田 佳弘 (やまだ よしひろ)
國學院大學
人間開発学部 健康体育学科 教授
研究分野:運動生理学、体育方法学(弓道)
論文
「人間開発学部学生の体力測定結果と主観的健康観や運動頻度との関連」
(2010/02/28)
「スポーツ場面における動作分析の視覚的フィードバックの有効性について」
(2008/03/30)
【國學院大學について】

國學院大學は、明治15年に創設された皇典講究所を母体とし、大正9年にわが国で初めて認可された私立大学のひとつです。文学部・神道文化学部・法学部・経済学部・人間開発学部の5学部13学科および大学院(文学研究科、法学研究科、経済学研究科)、さらに研究開発推進機構と教育開発推進機構を設置しています。グローバル化が進むなかで、國學院大學では異国文化理解にはまず自国文化の理解が必要と考えています。世界で活躍できるグローバル人材の育成をめざし、研究と教育を通じて日本の理解を深めると同時に、世界に対しての理解も深めていきます。
(引用:國學院大學紹介https://www.kokugakuin.ac.jp/about/introduction)
【國學院大學について】
國學院大學は、明治15年に創設された皇典講究所を母体とし、大正9年にわが国で初めて認可された私立大学のひとつです。文学部・神道文化学部・法学部・経済学部・人間開発学部の5学部13学科および大学院(文学研究科、法学研究科、経済学研究科)、さらに研究開発推進機構と教育開発推進機構を設置しています。グローバル化が進むなかで、國學院大學では異国文化理解にはまず自国文化の理解が必要と考えています。世界で活躍できるグローバル人材の育成をめざし、研究と教育を通じて日本の理解を深めると同時に、世界に対しての理解も深めていきます。
(引用:國學院大學紹介https://www.kokugakuin.ac.jp/about/introduction)


【インタビュイー】
山田 佳弘
(やまだ よしひろ)
國學院大學
人間開発学部 健康体育学科 教授
研究分野:運動生理学、体育方法学(弓道)
論文
「イギリス弓道界の活動状況教育プログラムの現状と課題」
(2017/02/28)
「スポーツ場面における動作分析の視覚的フィードバックの有効性について」
(2008/03/30)
世界各国で特許を取得した高度な映像処理技術と、誰もが直感的に操作できるインターフェイスを採用した映像分析ソフトウェア映像の撮影から分析、そして共有をダートフィッシュ・ソフトウェア1本で可能にします。
個人・法人問わず多くのお客様が、実際にカタログとソフトウェアをご覧になってからご購入いただいております。
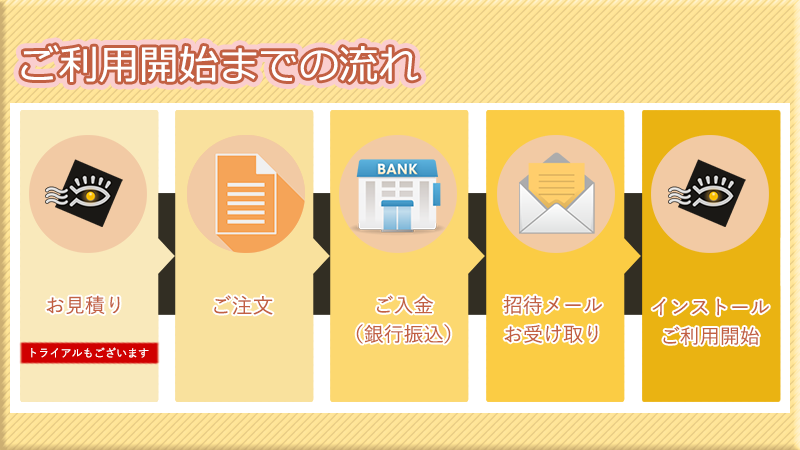
カタログ・資料はこちら
無料ダウンロードへ
随時資料を更新中